phaedra 50th Anniversary Edition (5CD+Blu-ray Audio)
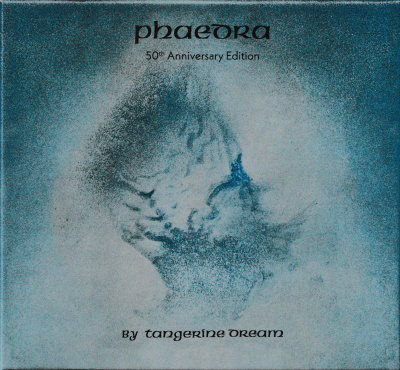
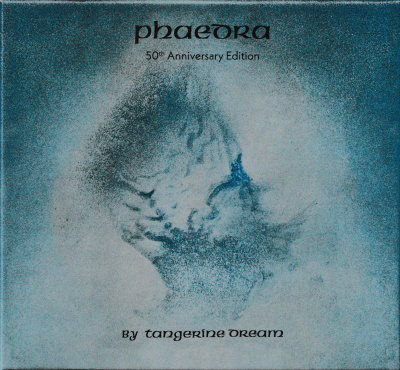
これ、初めて聴いたのは高校生の頃で、当然アナログLPでした。年代を見ると、「オーケストラ・チューブラー・ベルズ」より少し前ですね。当時ヴァージンは日本ではコロンビアで、割りと盛んに紹介されていたような気がします。ロバート・ワイアットやゴング並びにそのメンバーのソロ、デヴィッド・ベッドフォードは「星界の果て」だからもう少し後かな。
で、何かヴァージンのレコードで面白そうという理由で買ったのですが、衝撃でした。シンセサイザーってこんなことが出来るのか、と。特に表題作の「フェードラ」が凄い。明確な旋律は打ち出さず(最後のメロトロンの箇所にはちゃんとありますが)、低音の「シンセサイザー・リズム」の上に様々な電子音を乗せていく。これ、本当に人間が作った音楽なのかと、耳を疑いました。まさに、これとEL&Pの「展覧会の絵」が私にピアノを弾かせたようなものです。是非、シンセサイザーをやりたいと。
その後、「ルビコン」、「リコシェ」から点々と続いた彼らも、どうも段々つまらなくなったなあ、という感想を抱き、あんまり聴かなくなったのですが、さて……。
「フェードラ」が最高傑作という感想はずっと変わっていません。2005年版のリミックスでがっかりさせられたり、どうもライヴでは違うものになっていたりするのですが。
だから、長い間、これのサラウンドが出ないかなあ、と思っていたのです。電子音楽ってのはどちらかというと余り「現実的」でない(うまい言い方ではありませんが)音を使うでしょ? だから、「演奏者が前にいる」という様式を無視して独特な空間を作るのに向いている訳で、この「フェードラ」は最適だと思っていたのです。これは即手に入れなくてはなりません。
実は私、ヴァージンのアルバム、特にマイク・オールドフィールドは割りと輸入盤に拘るのですが、これは最初に通販で間違えて日本盤を買ってしまいました。それで輸入盤を買い直すことになったのですが、箱に入っているCDは国内盤はSHM-CDなんですよね。個人的には、聴いても違いは解らないのですが、棚には二つとも並んでます。いずれ売るのかなあ。
流石にサラウンドになると、音場が広がります。やはり、シンセサイザーは既存の楽器の代わりをする物ではなく、独自の使い方をすべきだと改めて認識させられました。周囲を包み込む音の広がりがとてもいいです。エドガー・フローゼが、「アクア」でバイノーラルのサラウンドに拘った理由がよく解ります。どうしてその後、サラウンドに進まなかったのか、マイク・オールドフィールドやピンク・フロイドはそちらに向かったのに。不思議に思います。
ところで別のことを一つ。これ、音声方式が二つ採用されていて、DTS-HDマスターオーディオとか言うのと、PCMです。それで、前者のDTS-HDでは二度ばかり再生機が停止しました。どうも、機械に負担がかかるみたいです。そこで、再生方式をPCMにしてからはエラーが出ていません。音の違いは特に判らず、ブルーレイが停止することがあるのは他にも報告されているらしいのでこちらで聴いていますが、まだまだ不完全なんですね。